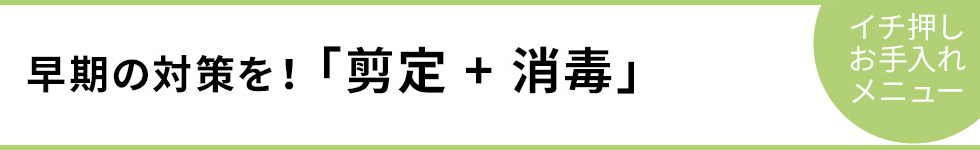
植物が成長する春から夏にかけて、病害虫の活動も活発になります。
被害を最小限に抑えるためには早期の対策が重要です。
庭木に消毒が必要、と聞くと驚かれるかもしれません。
消毒作業は大切な庭木を長く楽しむためにも大事なお手入れの一つです。

春から夏にかけて、庭木の枝葉が生い茂り、込み合うことで、病気や害虫が発生しやすくなります。
高温、多湿を好む病害虫は、ふだん目の届きづらいところから発生し、気がつかないうちに被害が広がるので注意が必要です。
病害虫を予防するためには、定期的に剪定をして、樹木の内部、下枝まで日当たりと風通しをよくしておくことが大切です。また剪定で不要な枝葉を減らすことで、万が一、病害虫が発生したときも様子の変化に気がつきやすく、早期に発見して対策を打つことが可能です。
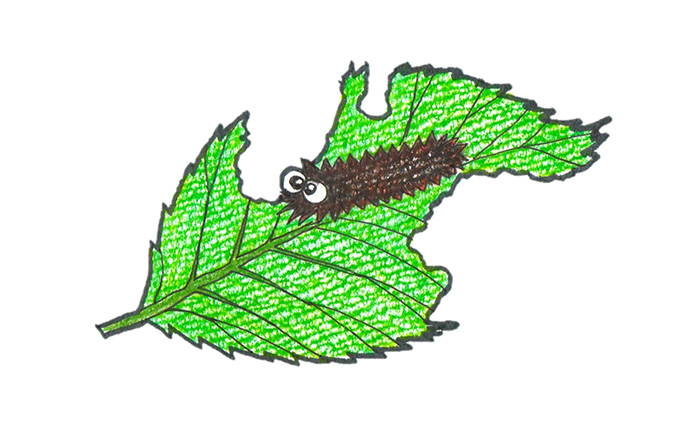
庭木に消毒をしないと害虫が発生し、葉を食い荒らす・害虫が出す排泄物で菌が繁殖し病気になるなどの被害が発生し、枯れることもあります。
害虫の中には庭木だけでなく人間に害を及ぼすことも。
「ツバキ」や「サザンカ」に発生することの多い「チャドクガ」の卵や幼虫には毒針毛があり、触れると激しいかゆみとかぶれを引き起こします。
毒針毛は風に乗って飛ぶことがあるので、近くを通ったり、洗濯物に付着していないか確認したり、日常的に注意が必要です。
チャドクガの写真を表示する ※害虫の写真が表示されます※
すでに害虫が発生している、または葉に虫食いのあとやフンの付着、枝葉の変色、部分的な落葉などが見られるときには、できるだけ早めに消毒・殺虫をすることをおすすめします。
松なら「マツカレハ(マツケムシ)」、桜なら「アメリカシロヒトリ」、ツバキなら「チャドクガ」などのように、樹木の種類によっては、発生しやすい病害虫がある程度決まっているので、予め発生時期を知って、予防のために消毒をしてもいいでしょう。くわえて、消毒をするときには、効果を高めるためにあわせて剪定をして、病害虫が発生しづらい環境を整えることも大切です。
適切なお手入れをしたうえで、日ごろから葉や幹の様子をよく観察して、大切な庭木を病害虫から守りましょう。

多くの害虫は冬以外の季節に活動しますので、病気や害虫の発生は主に春~秋にかけてとなります。
害虫を寄せ付けないためにも発生する前に予防しておきましょう。
具体的には、新芽の3月~5月と、害虫が発生しやすい7~9月におこなうのがおすすめです。
【害虫の発生時期】
カイガラムシ…年間を通して発生
アブラムシ…4~10月 ※特に春(4~6月)と秋(9~10月)に大量発生
ハダニ…5~11月
イラガ・チャドクガ…4~10月 ※特に春(4~5月)と晩夏(8~9月)に大量発生
【病気の発症時期】
うどんこ病…5~6月、9~10月
炭そ病…5~10月、特に梅雨(6~7月)、秋(9~10月)に発症しやすい
スス病…年間を通して発生、特に4~10月は発症しやすい
もち病…梅雨(5~6月)と秋(9~10月)に発症しやすい
できれば年1~2回の消毒をして、適切なお手入れで大切な庭木を病害虫から守りましょう。
《 この記事を書いた人 》
吉田 幸夫(よしだ ゆきお)
東京都府中市生まれ、府中市育ち。
大学卒業後、園芸用品メーカーで営業職を経験。その後、独学でSEOやデジタル広告運用を学び、現在は植木屋革命クイック・ガーデニングの営業部としてWEBマーケティング全般を担当。
趣味は散歩と森林浴。自然と触れ合う時間がアイデアの源泉になっている。